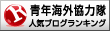開発途上国と呼ばれる国で2年間生活をしながら、その国の発展のサポートを行う青年海外協力隊。
そんな青年海外協力隊として、エチオピアとカンボジアで水泳指導を行っていた僕の経験・体験をご紹介♪
今回は「協力隊関係者で使われる専門用語」につてお話します!
本記事の内容
- 青年海外協力隊が使う専門用語15選。
✔ この記事を書いている人

Twitterはコチラから⇒Follow @yoshiswim05
大学(びわこ成蹊スポーツ大学)卒業後 ▷ 教員として勤務 ▷ 青年海外協力隊、アイルランドへワーキングホリデーなど計3年半の海外生活を経験した後、地元沖縄にて水泳のインストラクターとして働きながらブログを運営しています。
青年海外協力隊として生活を行っていると、日常では聞きなれない専門用語的なものが存在します。難しい用語などはなく、基本的には意味の理解・予測が可能な用語ばかりですが「知っていると良さそうな用語を15個」選んでみましたので、ご紹介します!
あわせて読みたい記事
1:青年海外協力隊が使う専門用語15選

青年海外協力隊(関係者)が使う専門用語15個を以下にご紹介します!
専門用語①
JOCV(じぇーおーしーぶい)
Japan Overseas Cooperation Volunteersの頭文字がとられた用語であり、【青年海外協力隊】という意味を表す。
【使用例】:協力隊員が自己紹介をする際などに「JOCVの〇〇〇です」と使われる。
専門用語②
SV(えすぶい)
Senior Volunteers(シニアボランティア:40歳から69歳まで)の頭文字をとったもので、【シニア海外ボランティア】を指す用語。
※シニアボランティアという呼び名は2018年ごろまで存在していましたが、現在(2021年)ではJICA海外協力隊という1つの呼び名に統一されているようです。
詳しくは⇒JICAホームページをご確認ください。
専門用語③
職種(しょくしゅ)
青年海外協力隊として海外に派遣される際に、【実際に活動する種類】を指す用語。
【僕の場合】:水泳という職種で協力隊に参加していました。
青年海外協力隊事業はさまざまな職種があり、教育系の物から地域のコミュニティーを活性化させる目的のもの、スポーツ・農業・工業・医療など幅広いな分野・種類を扱っています。
専門用語④
要請(ようせい)
青年海外協力隊として、途上国で行う【活動の内容】をさす用語。
青年海外協力隊の活動には要請書と呼ばれる「求められている活動や目標」・「活動先の環境やボランティアを派遣することになった経緯」などが記載された用紙があり、それをもとに活動を行っていきます。
【僕の要請内容】:水泳の競技力向上と普及活動
専門用語⑤
隊次(たいじ)
青年海外協力隊が【海外に派遣される時期】を表す用語。
協力隊では、いくつかの隊に分けて海外派遣が行われます。そのため派遣される時期で隊次分けがされています。
※2021年現在では制度の変更があり、年に3つの隊次に分けられているそうです。
| 隊次 | 派遣時期 |
| 1次隊 | 4~6月ごろ |
| 2次隊 | 9~11月ごろ |
| 3次隊 | 1月~3月ごろ |

専門用語⑥
任期(にんき)
協力隊としての【活動の期間】を表す用語。
青年海外協力隊の活動期間(任期)は原則2年間ではありますが、短期ボランティアと呼ばれる「短い期間の活動」を行う隊員さんも存在することから、必ずしも2年間の任期でないこともあります。
▽短期ボランティアについて知ることが出来る記事です。ぜひご覧ください。▲
専門用語⑦
訓練所(くんれんじょ)
青年海外協力隊の選考試験合格後に行われている、【語学やボランティアに関する知識を習得するための研修】を表す用語。
訓練所には「福島県:二本松」と「長野県:駒ケ根」に2か所があり、それぞれの派遣される国や習得が必要な言語により振り分けがされます。研修期間は約2か月半と長期的な研修となっています。
▲協力隊派遣前訓練についての詳しい情報は以下の記事をご覧ください▽
専門用語⑧
任地(にんち)
青年海外協力隊として【自分自身が派遣される国・地域】を表す用語。
「○○という国の○○という町」(例:日本の大阪)のような感じで、協力隊としての活動の拠点となる場所が任地となります。そのため、協力隊生活中は自分自身の任地についての話を多くすることになると思います。
専門用語⑨
CP(カウンターパート)
派遣された国で活動を共に行う【現地人のパートナー(同僚)】のことを指す用語。青年海外協力隊は1人で活動を行っていくのでなく、CP(カウンターパート)と呼ばれる現地人の方と協力を行いながら活動を行います。
【理由】:2年間という限られた期間のみしか協力隊は原則存在しません。そのため、協力隊が日本に帰国した後も継続した活動が現地の方のみで行えるように、CP(カウンターパート)に知識・技術などを提供を行うことが目的とされる。
※CP(カウンターパート)は派遣される場所によりすごく差があり、「年齢が若い方」や「活動場所の期間の中間の立ち位置にいる方」であることが多いですが、場合によっては「施設のトップの方」や「CP(カウンターパート)がいない」という場合も存在します。
専門用語⑩
VC(ボランティア調整員)
青年海外協力隊の【現地での活動・生活が円滑に行えるように調整等を行ってくれる日本人スタッフ】の事を表す用語。
VC(ボランティア調整員)さんは密接に関わる存在となり、2年間の間に発生した問題・悩みなどを相談したり解決への方法を一緒に考えてくれる方たちです。
専門用語⑪
報告書(ほうこくしょ)
青年海外協力隊として任期中(海外派遣中)に【定期的に提出が義務図けれれている報告書類】を表す用語。
2年間の協力隊生活中に5回の提出が定められています(派遣3カ月・半年・1年・1年半・帰国前)。報告書の内容は提出の時期によって異なりますが、「活動の状況」「今後の活動の計画」をメインに書類作成が行われます。
※報告書は提出後、「別の協力隊員が報告書を作成する際の参考資料」や「JICA事業に興味がある方が閲覧する資料」として保管されるため、しっかりと作成する必要のある書類となっています。
▲報告書に関するさらに詳しい情報は以下の記事をご覧ください▽
専門用語⑫
任国外旅行(にんこくがいりょこう)
青年海外協力隊の任期中に年に20日間ある【自分の派遣されている国から離れて旅行が行える制度】を表す用語。
任国外旅行の主な目的として、「自分の住んでいる国以外の国の文化」や「自分の国との違い」を感じる事・「日頃の生活・活動でのストレスを解消」することなどがあげられ、多くの協力隊員の方がこの制度を利用し旅行に出かけます。
※任国外旅行はあくまで自主的に利用できる制度であるため、「費用は全額自己負担」となります。
▲任国外旅行についてのさらに詳しい情報は以下の記事をご覧ください▽
専門用語⑬
任短(にんたん)
青年海外協力隊に定められた任期を、様々な理由により【任期を短縮し日本に帰国】することを表す用語。
任短(任期短縮)の主な理由としては「健康上の理由」が1番多いと思いますが、それ以外にも「家族の事情」や「自信の心情の変化」など多くの理由があります。常に変化する協力隊での生活。原則2年間の任期ではありますが、自分の将来を考えて任短することも選択肢の1つとして存在します。
専門用語⑭
○○隊員(〇〇たいいん)
協力隊同士で、【その人の特技や特徴をなどを表す際にネタ】として使う用語。
【使用例】:「カフェが好きでよくカフェに行くから=カフェ隊員」「お洒落さん=お洒落隊員」「よく寝るから=睡眠隊員」など、その人の癖や特徴・趣味なども〇〇隊員と表し話のネタとして使います。
※協力隊の活動とは全く関連のない言葉ではありますが、隊員同士のコミュニケーションの1つとして使われている言葉程度に覚えておくとよいかも…
専門用語⑮
OV(おーぶい)
スポーツの世界などで使用される、現役を引退した選手などに使われるOBやOGと同様【青年海外協力隊の活動を終了した元協力隊員(Old Volunteer)】の事を表す用語。
青年海外協力隊の事業では、「日本帰国後の日本への還元」という項目が定められており、途上国での2年間が終了してもOVとして日本で協力隊の経験が活かされるような活動が求められています。

青年海外協力隊の活動・生活は、日本の生活等とは異なる部分がすごく多いため、日常的に使われない言葉などもいくつかあります。しかし、基本的には難しい用語などを使用することはなく、例え用語を知っていなくても「そこまで支障はありません。」
JICA関係者や隊員同士でのコミュニケーションを図るうえで、用語を知っておくと話がスムーズに行えたりする可能性はありますがその程度です。
そのため、今回ご紹介した15個の用語は必須で覚える必要などはありませんので「こんな言葉も使うんだな。的な感覚」で記事を読んでいただけていたら幸いです。
▲青年海外協力隊に関する書籍も販売されています。気になる方はぜひチェック!▽
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
この記事が『面白かったな』『役に立ったな』と思った方は是非SNSでのシェアお願いします。
それでは
YOSHI@