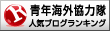青年海外協力隊の活動の様子について気になる方はいませんか?
発展途上国と呼ばれる国で2年間ボランティア活動を行い、その国の発展の支援を目的とする青年海外協力隊(JICAボランティア)。日本政府が行っている活動(ODA)ということで、一度は耳にしたことがあるという方も多いボランティアの一つかと思います。
そんな青年海外協力隊として東アフリカのエチオピアで水泳隊員として活動していた筆者。「水泳隊員ってどんな活動をするの?」と疑問を感じる方もいるかもしれません。
そこで今回は「エチオピアの水泳隊員の活動」というテーマで、エチオピアで水泳隊員として活動していた筆者の様子をご紹介します!
青年海外協力隊の水泳隊員について興味がある方にとって有益な情報になること間違いなしですので、ぜひ最後まで読んでいただければと思います。
✔ 本記事の信頼性

本記事を書いている僕はブログ暦5年。青年海外協力隊への参加をきっかけにブログを始め、現在では約300記事ほど作成しました。僕の経験が誰かのお役に立つことを目標にこのブログを運営しています。
Contents
青年海外協力隊、エチオピア水泳隊員の活動とは?

青年海外協力隊、エチオピア水泳隊員として活動していた筆者の現地での様子をご紹介していきます。
「競技力向上」をメインに指導を求められる
水泳の競技力向上+水泳の普及活動が活動内容
協力隊の水泳隊員としてエチオピアに派遣されるにあたり、エチオピア側からは「競技力向上」をメインに活動を求められていました。それに加え水泳人口の少ないエチオピアでの普及活動も可能な限り行ってほしいという要望がありました。
エチオピアの水泳環境は「ひどい状況」
結果的にエチオピアでの活動は1年で区切りをつけることに
通常派遣された国で2年間活動行う協力隊事業ですが、筆者の場合「1年でエチオピアでの活動に見切りをつける」結果となりました。理由についてはいろいろあるので別記事にてお話させていただきます。
当時のエチオピアの水泳事情
・配属先(活動を行う場所)のプールが故障で利用不可
・別施設での練習等が行われる予定でしたが、資金面の状況により利用がほぼできない状況(月1~2の練習回数)
・別施設への移動手段の問題(選手を連れていく手段がない)
元々活動の拠点だった場所で活動ができないことに加え、配属先もプールの修繕にあまり乗り気ではない(資金の問題)などから、ほとんど水泳の指導は行えず1年間のエチオピアでの滞在中に30回指導できたかどうか?程度の回数しか水泳指導はできませんでした。
水泳隊員としては「やることのない状況」と言える時間が多くあり、結果的にエチオピアを離れ別の国で活動を行うこととなりました。

少ない回数の中で活動を一緒に行った人たち
現地人コーチ1人・水泳選手10名と活動を行った
先ほどのお話した通り、いろいろな問題がありほとんど水泳隊員として水泳指導に当たることはできませんでしたが、少ない回数の中で一緒に活動を行っていた人たちは「現地人コーチが1名+水泳選手10名」でした。
 一緒に活動を行ったコーチ・選手達
一緒に活動を行ったコーチ・選手達
現地人コーチ(カウンターパート)
僕のカウンターパート(活動を行う際のパートナー的存在)となる、この現地人コーチ(40代)の過去の職は警察官。しかし警察官であった当時、事件に巻き込まれ左足を失い警察を続ける事が不可能になったことから水泳のコーチになったという悲しい過去の持ち主で、左足が股下から完全に無い状況でした。
水泳選手たち10名
エチオピア各地からスカウトされ集められた子供達で、施設から食費・宿泊費・給料が支払われているという好条件の元、スポーツを行っている12歳から20歳ぐらいまでの年齢の子供たち。水泳のレベルとしては日本の一般小学生程度で高いレベルではありませんでした。
練習回数がほとんど確保できず月1,2回程度しか顔を合わせることもありませんでしたが、筆者の名前「ヨシ!ヨシ!」を呼んでくれて、楽しく関りを持つことができました。100%の信頼関係は気築くことは出来ませんでしたが、選手達の事は凄く大事な存在でした。
水泳隊員としてできることを探した活動期間

エチオピアの水泳隊員として派遣されたものの、当初の要請の内容と全く異なり正規の活動が全くできない状況。そのため正規で行う予定の活動以外で「自分が水泳隊員としてできそうなこと」を探しながらエチオピアでの時間を過ごしました。

エチオピア水泳連盟にアプローチ
アプローチするも水泳連盟は機能しておらず
筆者の配属先の機関がエチオピアの水泳連盟とは別機関であることから「水泳連盟にアプローチをかければ何かできるかも?」と考え、水泳連盟に話をしに行くことに。しかし、当時のエチオピアの水泳連盟は無期限の活動休止を行っており、まったく活動につながる機会を得られずでした。
活動無期限休止の理由
当時(2016年)のエチオピア水泳連盟はその年にあったリオ オリンピックに出場した選手が不正(賄賂など)を使いエチオピアの代表権を獲得したとされる疑惑がかけられ、国民からバッシングを受けたことにより、無期限の活動休止を行っていた。
\問題となった選手に関する記事はコチラ/
水泳ができる環境を求め地方へ
首都アディスアベバを離れ、地方都市へ調査をするも厳しい状況
当時、僕が生活を行っていた場所は首都のアディスアベバ。そのため、アディスアベバ以外の地域で水泳ができる環境を探してみることに。水源の確保がもともと難しいアフリカという土地柄、地図なども見ながら水源が確保できそうな地域へ行き、「水泳用プールがあるか?」などの調査を行いましたが、結果として活動に繋がりそうな場所は発見できませんでした。
 水の無いプール
水の無いプール
また電話でも「水泳用プールが無いか?」いくつかの地域のスポーツ関連施設に電話で問い合わせを行ったところ「生活用の水の確保も難しいのに、水泳なんかできるか!」と一刀両断されてしまいました。

水泳指導者研修会に同行する
経路不明の水泳指導者研修会に同行し講師を行う
開催経路や理由などは全くもって不明でしたが、筆者のカウンターパートからの連絡で「水泳指導者講習会が開かれるから同行してくれ」ということで、講師として同行することに。
※講習会の主催は一応水泳連盟となっていたことから、エチオピア水泳連盟の適当さのようなものを感じました。
エチオピア全土から集められた講師に対して「水泳の理論と実技指導」を講習する内容で、1週間にわたり行われました。地方都市のホテルに併設されたプールにて行われました。
講習参加者の方たちは真剣に1週間水泳の勉強をする姿に「エチオピアにこんなにも水泳に興味を持ってくれる人がいるんだ」と嬉しくなりました。
またその期間がっつり交流などもでき筆者としても良い思い出にもなりましたが、筆者のカウンターパートを含め「講習会を持つための準備が不十分」な面も多く、少し勿体無い講習会でもあったと感じます。
 講習会の様子
講習会の様子
こういった研修会が定期的に行うことができれば、エチオピアの水泳の発展に大きく貢献されそうですが、次回の開催は未定とのことで「予算」や「水泳連盟の問題」からできても1年に1回が限界とのこと。
筆者がエチオピアに滞在している間には次回の予定が立てられることはありませんでした。
\この講習会についてさらに詳しく紹介した記事はコチラから/
水泳の普及活動を地域の幼稚園で実施
視点を変えて水泳の普及活動を行う
水泳用プールを探したりするものの、なかなかいい結果に繋がらないことから「視点を変えて普及活動を行ってみたら?」ということで、普及活動に目を向けてみることに。
地域の幼稚園に行き、「水泳に関する絵本の読み聞かせ」や「水泳用品の紹介」を行い水泳というスポーツを知ってもらう活動を行いました。
 活動の様子
活動の様子
本来ならば、子供たちをプールに連れていき水泳の指導を行ったりが普及活動と言えるかもしれませんが、それが困難な状であることから「とりあえず水泳を知ってもらう」ということも目標に活動を行いました。
この活動が水泳人口の増加につながる感覚はありませんでしたが、子供たちの反応は良かったの将来的に水泳の人口が増えてくれたらと願っています。
\普及活動のさらに詳しい内容はコチラの記事をご覧ください/

エチオピア水泳隊員として得たもの

今回は「エチオピア水泳隊員の活動」について筆者自身の経験をお話させていただきました。エチオピアに派遣された時点で予定とは全く違う状況から、「活動ができない」という悶々とした日々の連続でした。
その中で「自分にできることは?」と諦めずに活動を探した日々は、今となればすごくいい経験だったなと感じています。
順調に活動が行えている他の隊員さんと比べると、羨ましさや焦りなども抱くことも何度もありましたが、その経験があったこそ「絵本で水泳を普及する活動」や次に派遣されることとなる「カンボジアでの活動」に繋がったと感じています。
\任国変更を行いカンボジアへ移動した経緯などはコチラの記事をご覧ください/

協力隊の活動は「何が起きるかわからない」
青年海外協力隊として発展途上国での活動・生活は「何が起こるか分からない」です。
しかし、その状況を「諦めず自分が出来ることを行う」ということがすごく大切で、それを行うことで物事もいい方向へ進んでいくと筆者は感じています。「何が起きるかわからない」ということは頭に置きながら途上国での生活を行ってください。

-----Please check it ------
僕のInstagramでは、これまでの旅先での写真を公開しています。ブログの記事には載せていない写真なども多く投稿されていますので、ご覧いただけたら嬉しいです!またフォローも大歓迎です!
この投稿をInstagramで見る

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
この記事が『面白かったな』『役に立ったな』と思っていただけたら嬉しいです。
それでは
YOSHI@