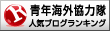青年海外協力隊(JICAボランティア)の選考試験について気になる方はいませんか?
発展途上国と呼ばれる国で2年間ボランティア活動を行い、その国の発展の支援を目的とする青年海外協力隊(JICAボランティア)。日本政府が行っている活動(ODA)ということで、一度は耳にしたことがあるという方も多いボランティアの一つかと思います。
そんな青年海外協力隊ではありますが、「ボランティアの参加方法や選考試験の内容ってどうなっているの?」と疑問を持たれる方も多いかもしれません。
そこで今回は「青年海外協力隊の選考試験の内容」というテーマで、協力隊に参加するまでの流れや選考試験の内容などについてご紹介します!
青年海外協力隊に興味がある方にとって有益な情報になること間違いなしですので、ぜひ最後まで読んでいただければと思います。
✔ 本記事の信頼性

本記事を書いている僕はブログ暦5年。青年海外協力隊への参加をきっかけにブログを始め、現在では約300記事ほど作成しました。僕の経験が誰かのお役に立つことを目標にこのブログを運営しています。
Contents
ザックリ解説。青年海外協力隊とは?

青年海外協力隊について全くわからない。という方でもザックリと「協力隊とは何か?」が理解できるように解説していきます。
日本政府が行う政府開発援助(ODA)制度
青年海外協力隊は日本国政府が行う政府開発援助 (ODA) の一環として、外務省所管の独立行政法人国際協力機構 (JICA) が実施する海外ボランティア派遣制度の事を指します。(英語表記では:Japan Overseas Cooperation Volunteers)
海外ボランティア制度と言ってもその活動の種類は様々で、募集を行っている分野には、農林水産、人的資源、保険・医療、教育、スポーツなどあり延べ120以上の職種に分かれています。また派遣される国々も、アジア・アフリカ・南米・ヨーロッパなど様々です。
1965年より開始された青年海外協力隊事業ですが、2018年までに91ヶ国、計43,864名の隊員を派遣し各国の発展へのサポートを行っている事業です。

協力隊の選考試験の応募から合格までの流れとは?

青年海外協力隊になるためには、選考試験の受験・合格をすることが必須となっています。そこで、選考試験の申し込みから合格までについて詳しく解説していきます。
青年海外協力隊の応募資格について
青年海外協力隊の選考試験への応募資格はすごくシンプルで、「20歳~69歳までの日本国籍を持つもの」となっています。そのためこの条件に満たしている方は、どなたでも協力隊の選考試験を受験することが可能です。

実際、青年海外協力隊の活動は多くの職種が存在し、その職種の内容や現地での活動のレベルなどでも求められる人材は大きく異なります。そのため、受験者がその基準(経験や資格など)に達していなければ合格できません。
ココがポイント
協力隊の選考試験は基本誰でも受験が可能だが、受験を希望する職種や内容によって、選考試験の合格の基準は大きく異なる。
選考試験の出願から合格までの流れについて
青年海外協力隊の選考試験の出願を行ってから、実際に試験合格までの主な流れは以下の通りです。
「応募」 ▽ 「1次試験」(書類審査) ▽ 「2次試験」(面接・健康審査) ▽ 「合格」(協力隊候補生) ▽ 「派遣前訓練」(語学等の訓練) ▽ 青年海外協力隊として途上国へ派遣
上記の流れが試験の出願から合格までです。
※さらに詳しい情報は青年海外協力隊の公式ホームページをご確認ください。
協力隊 選考試験の内容とは?

青年海外協力隊に参加するための選考試験の内容について詳しくお話していきます。
※筆者の体験談を含みます。
1次試験(応募調書)について
協力隊の選考試験の1次試験は書類審査となります。書類審査で提出する書類は以下の通りです。
1次試験(応募調書)
- 志望動機について
- 語学力について
- 自身の健康について

志望動機について
応募調書でまず記入を求められるものが「志望動機」です。1次試験提出書類として以下の内容の記入が求められました。※筆者受験2016年当時です。
・ボランティア活動に参加する動機、抱負
・ボランティア活動の意義、目的
・この職種を選択した理由
・選択した職種に対する経験やセールスポイント
・選択した職種に関する弱点
・自己PR
・帰国ボランティアの話などから心に残ったエピソードや自分自身の活動に取り入れたいこと
・どのようなボランティア活動を行いたいか?
・帰国後に協力隊参加経験をどう活かしたいか?
以上の項目を150~200文字程度(各)にまとめて記入しました。
ココ大事!
「自分が協力隊になりたい理由」や「協力隊でやりたいこと」などを明確にしておくことが必要になります。文章にして専用用紙に記入もしますので簡潔にわかりやすく説明できることが大切です。
受験する職種によっては「技術調書」や「職種別試験」と呼ばれる専門的な知識・技術をどれだけ持っているか確認するための用紙の提出を求められる場合もありますが、筆者が受験した水泳という職種ではどちらの書類提出も求められませんでした。
語学力について
青年海外協力隊の1次試験では「自身の語学力」に関しても応募用紙に記入が必要となります。希望する国や活動の内容(職種)によっても求められる語学力は異なるようですが、応募の際の最低レベル「英検3級程度もしくはTOEIC330点(中学卒業レベル)」の語学力があれば基本的に受験が可能とされています。
また英語以外の言語(スペイン語やフランス語など)の語学テストのスコアなども書類記入が可能です。また語学外の資格に関しても記入する項目がありますので、そちらも記入できるだけ記入しましょう。
筆者の記入した資格
✔ TOEICスコア(355点)
✔ 英検準2級
✔ 教員免許
✔ 泳力検定1級
✔ 日本体育協会認定 スポーツリーダー
✔ 公認スポーツ指導養成講習修了書
✔ 健康運動指導士
筆者の場合、受験職種が水泳ということで記入した資格は水泳もしくは体育・スポーツに関わる資格を選んで記入を行いました。どんな資格でもとりあえず書いてみるのは大事かもしれません。
ココ大切!
語学力に関しては、選考試験終了後に行われる派遣前訓練にてしっかり勉強を行うため、受験時点での語学力は重要視されていない印象があります。(語学力があるに越したことはないですが…)
自身の健康についての調査
健康に関する審査内容としては「健康診断の受診が必須」となります。また青年海外協力隊の1次試験の項目の中で健康診査が1番厳しいとされています。
理由としては、開発途上国で2年間安全に生きていくためには健康状態の良し悪しはすごく重要な項目であり、2年間の間に体調を壊される方も協力隊の中には多く存在します。またストレス耐性なども絶対に必要な能力で「日本と違った環境の中で健康に活動が出来る状態」であるかどうかの判断をこの健康調査書を使って審査しているようです。
ココ大切!
青年海外協力隊の選考試験では「肥満」「血液の数値が悪い」などのいわゆる健康状態が悪いという事ももちろんダメではありますが、「やせすぎ」などの場合も選考から漏れる可能性があります。

ゆっくり時間をかけて記入が必要になるかと思いますので、時間に余裕をもって取り組んでください。
2次試験(面接)について
選考1次試験を無事通過された方は、2次試験へと進むことが出来ます。2次試験は面接試験となっていますが、以下の2種類の面接を行っていきます。
2次試験(面接試験)
- 面接(人物面接・技術面接)
- 技術試験 ※職種による
受験する職種によっては技術試験が、実技(主にスポーツ系)や作品の提出などを求められる場合もあります。筆者の受験した水泳では実技はせず口頭で水泳に関する知識について応答を行う面接形式の試験のみでした。
人物面接について
どの職種を受験する方も共通で受験する「人物面接」と呼ばれる試験ですが、主に「この人がどういう人なのか?」を見極めるための試験だと言われています。いわゆる普通の面接です。
この人物面接のうわさではありますが、面接管の1人は「心理系」や「精神鑑定」専門家の方で、受験者の行動や発言などを専門的な視点(心理学・精神鑑定)で観察し、評価していると噂されることもあります。
筆者の体験談
筆者が面接試験を受験した際には1対2(面接官)の形式で、約15分~30分程度の時間の面接を行いました。内容としては1次試験時に提出した書類に沿ってような質問(志望動機やボランティアについての考え方など)を主にされました。

技術面接について
受験する職種・分野での知識・技術の有無やレベルを見極めるために行われる「技術面接」ですが、職種によっては実技を行ったり、作品の提出を行ったりする場合もあります。
筆者の経験談
筆者の受験した水泳という職種は、実技試験ではなく口頭にて水泳指導に関する知識や技術に関する質問に答える形式の試験となりました。時間としては人物面接と同様15分~30分程度で1対2形式でした。
ココ大事!
技術面接の試験管の方は、その分野の専門家やプロの方がされています。そのためごまかし等は一切聞かないので、自分の受験する職種・分野の基礎的な知識+自分の考えや意見をうまく伝えられるような準備は絶対に必要です。

青年海外協力隊は誰にでも参加の可能性がある

今回は「青年海外協力隊の選考試験」について詳しくお話しました。1次試験・2次試験と合格を得る必要がありますが、受験資格に関しては「満20歳から69歳の方で、日本国籍を持っている方であればどなたでも参加する資格」があるため、基本的には誰でも受験が可能です。

そんな誰にでも可能性があるからこそ、「自分には何ができるのか?」「どんな支援ができるのか?」と深く考える必要があり、「開発途上国の為に自分の経験や技術を活かしたい」と強く感じる方は、青年海外協力隊はその思いを形にできる選択肢の1つだと思います。そして、そんな熱い気持ちを持つ方が青年海外協力隊になることを期待しています。
高い専門知識や技術だけではなく、「誰かの為になりたい」という気持ちが強いことが青年海外協力隊の試験に合格するポイントの一つだと僕は思っているので、そんな思いを持たれている方は、ぜひ青年海外協力隊にチャレンジしてください。

-----Please check it ------
僕のInstagramでは、これまでの旅先での写真を公開しています。ブログの記事には載せていない写真なども多く投稿されていますので、ご覧いただけたら嬉しいです!またフォローも大歓迎です!
この投稿をInstagramで見る

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
この記事が『面白かったな』『役に立ったな』と思っていただけたら嬉しいです。
それでは
YOSHI@